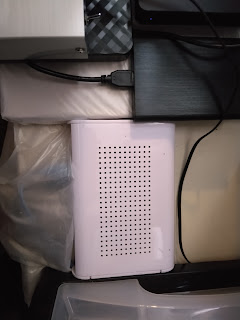結構レコードを聴いていなかったので、立て続けに聴いてしまいました。
今日は、クラシックを聴いてみました。
1枚目は、テラーク方式録音盤(ロミオとジュリエット)(チャイコフスキー、くるみ割り人形)です。
テラーク方式は、現在の各楽器を夫々収録する、マルチマイク方式と違い、奏者のオーケストラから、バランスが取れて聞こえる位置にワンポイントマイクを立てて録音しています。
各楽器の定位が素晴らしく、特に低音楽器の重低音がはっきり録音されています。
ただし、ピアニッシモからフォルテシモのダイナミックレンジが大きく、再生側も能力がないと音が割れてしまうか、爆音になってしまいます。
再生機器のウーハーは、TAD40㎝ダブルタンデム方式で能率も100dB有るので、揺れるような重低域再生、106dB高能率ホーンの中高域、音場が崩れることなく再生されます。
くるみ割り人形は、皆さんも、よく知っている親しみのある曲と思うので、解説は不要と思います。
このテクニカのMCカートリッジAT33E、過去にターンテーブルに針を落下させ、破損してしまったアクシデントが有り、これに友人が新たに針を取り付けてくれたのです。
天才の友人は、40年選手になる、カートリッジの内部を清掃してくれ、トレース能力も上がっています。
さて再生機器の話はそこまでで、2枚目はヨハンシュトラウス、ウインナーワルツ、シリーズ(美しき青きドナウ)です。
ヘルベルトカラヤン指揮、ウインフィルの演奏です。
このレコードはグラモフォンの録音盤で、発売当時2000円シリーズのクラシック盤でした。
若きカラヤン指揮で、ウインフィルの演奏も、録音も素晴らしくて、レコードの価格が2000円と、3拍子ならぬ、4拍子揃ったアルバムです。
3枚目は、先ほどのカラヤンの愛弟子、先日、他界された巨匠、小澤先生がボストン交響楽団で指揮した(ホルストの惑星)です。
それまで指揮は、レナードバーンスタインでしたが、小澤先生に代わって、指揮者が代わると楽団そのものが変わると言われる、お手本のようなアルバムです。
これが今までのボストン交響楽団と思うような、とてもダイナミックで素晴らしい演奏です。